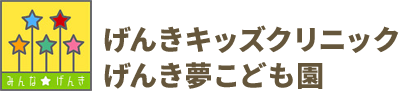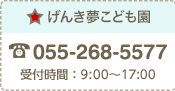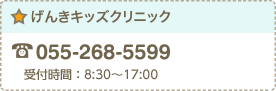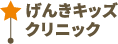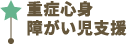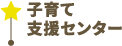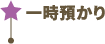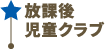令和元年10月号(Vol.173)
オトナのⅤPⅮ(ワクチンで防げる病気)
先月クリニックで、季節外れのインフルエンザ感染者が出て大変驚きました。幸い重くなる人は少なく安心しました。近くの園や小学校でもインフルエンザによる学級閉鎖等の報告がありました。また同時期に沖縄ではインフルエンザ警報が発表されたそうで、今後の発生状況に注意する必要があります。
先月、ここ数年恒例になったSSPE(亜急性硬化性全脳炎)という難病の親の会が主催するサマーキャンプに妻と娘と一緒に参加してきました。患者さんの父親から今年1月、お子さんが成人式に出席した話を聞きました。「この病気にかかり車いす生活となったことで、自分も付き添いで成人式に参加することができよかった。この病気にならなければ自分が参加することもなかった。」と何事にも前向きな父親からの話でした。このような両親に見守られているお子さんを本当に幸せだと感じ、今後もこの親の会を応援したいと思いました。
日頃このコラムでは子どものことを中心に書いていますが、今月は育児をする親に目を向けたいと思います。予防接種は以前に比べて、多くの種類が存在していて、そのほとんどは0歳~1歳のお子さんに接種しています。一方で昨年、大人の予防接種について推奨するホームページ(オトナのVPD)が開設されました。予防接種は子どもだけではなく、大人も大切なものです。
オトナのVPDって
VPD(Vaccine Preventable Disease)とは「ワクチンで防げる病気」のことです。現在、多くのワクチンがありますが、接種すれば免疫が獲得され病気にかかりづらい体になります。VPDにかかっていない場合、子どもだけでなく、大人もワクチンを接種することが重要です。
オトナのVPDのホームぺージには「思春期・青年期(10~20代)」・「子育て世代」・「現役ミドル世代(40代~)」・「シニア世代(60代~)」と年齢別に4つ分かれています。自分の世代をクリックするとお勧めのワクチンが記載されています。読者の世代である「子育て世代」では麻しん・風しん・おたふくかぜ・水痘は大人でかかると重くなるので2回接種を勧めています。『妊婦さんにはインフルエンザワクチンをすることで、移行抗体で新生児の赤ちゃんを予防する効果があること』・『家族やパートナーがB型肝炎キャリアの場合は直ちにB型肝炎ワクチンを接種すること』・『子どもの時期に接種したワクチンの中で日本脳炎や破傷風は大人になると免疫が低下するため、日本脳炎流行地域に渡航する場合は追加接種をすること』・『破傷風は災害でのボランティア活動時は事前にワクチン接種をすること』が勧められています。
シニア世代には重症化しないようにインフルエンザワクチン・肺炎球菌ワクチン・帯状疱疹後の神経痛はつらい症状が長く続くため水痘ワクチンを勧めています。
思春期・青年期のお勧めワクチン
子育て世代と同様に麻しん・風しん・おたふくかぜ・水痘のワクチンを2回接種することだけでなく、性交渉などでB型肝炎が感染するのでB型肝炎ワクチン3回接種をお勧めしています。
さらに、子宮頸がんの原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)感染症を予防するHPV(子宮頸がん)ワクチンもお勧めです。子宮頸がんは性交渉によってHPV(ヒトパピローマウイルス)に感染し、持続感染することでがん化するVPDです。日本での患者数は年間約1万人、20代後半から増加し40代以降は概ね横ばいになります。早期に発見されれば比較的治療しやすいといわれていますが、年間約3,000人が死亡しています。
HPVワクチンは6年前から小学6年生から高校1年生までを対象に定期接種となりました。その2か月後、接種後の慢性疼痛などの有害事象報告があり、一時的に積極的な勧奨接種が差し控えられています。しかし、一方で現在でも定期接種のワクチンとして原則無料で受けることができます。副反応出現時には定期接種として救済します。HPVワクチン接種後の慢性疼痛などの症状とワクチン接種には科学的な因果関係がないことが国内の研究でも明らかになっています。3年前に名古屋市が7万人以上を対象に大規模な疫学的研究(名古屋スタディ)を実施した結果、HPVワクチン接種後にワクチンとの関連が疑われた症状の発生頻度はワクチンを接種した人とワクチンを接種していない人の間で違いが認められませんでした。関連学会などが勧奨接種の再開を国に求めています。日本で認可されているHPVワクチンは2価(HPVウイルス2種類)と4価(HPVウイルス4種類)で7割の効果がありますが、現在、アメリカでは9価(HPVウイルス9種類)ワクチンに変わり、9割の効果があると言われています。日本でも早く勧奨接種が再開され、9価ワクチンになることを切望します。
参考文献
「オトナのVPD」ホームページ http://otona.know-vpd.jp/