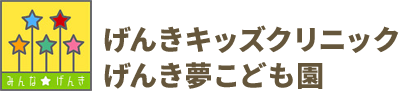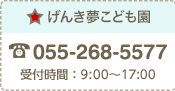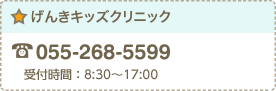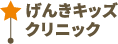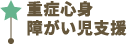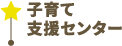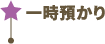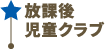令和7年6月号(Vol.241)<br>教育虐待について
今月は梅雨もあり、祭日もないので一月が長く感じますね。
子ども達は学校・園での疲れもたまってくる頃かもしれません。お子さんの訴えには耳を傾け、学校・園でお子さんの困り感があった場合はご両親がお子さんの声を汲み取り、時には先生に伝えることで子どもの不安な気持ちが和らぐことがあります。ぜひ向き合ってみて下さい。
3年前にうちの庭にサクランボの木を植えました。2年前は実ができる前にアオムシに葉を全部食べられてしまいました。今年は消毒をして、なんと初めてたくさんの実が生りました。とてもうれしい気持ちで明日にでも味見しようと考えていたある日、実をカラスにすべて取られていました。サクランボ農家の方に聞いて来年はネットをかけて対策しようと考えています。
我が家は娘が中学生になり、帰りは部活が終わって午後6時過ぎに帰宅、週2回で朝練もあり、小学校の時と様変わりの生活です。娘は学校にいる時間が長くなり、夫婦2人でいる時間も多くなってきました。少ないながらも子どもと接する時間を大切にしたいと思います。
先月、東大前駅刺傷事件がありました。43歳男の動機が子どもの心身が耐えられる限度を越えて教育を強制する「教育虐待」が原因で、罪を犯したと供述しています。教育熱心な親の下で中学時代に不登校になって苦労したこと・小学生の頃、テストの点数が悪いと親に厳しく叱責されたようです。今月は「教育虐待」について皆さんと考えていきたいと思います。
教育虐待いろいろ
「東大前駅刺傷事件」以外にも、2018年滋賀県守山市で母親が国公立大医学部への進学にこだわり、約9年間浪人させたことで元看護師の長女が母親を殺害した「滋賀医科大学生母親殺害事件」、2023年には九州大学に通う19歳の大学生が佐賀県鳥栖市の実家で両親を殺害した事件がありました。きっかけは幼少期から父親による心理的、身体的な虐待を受けており、事件4日前に大学の成績が下がったことで1~2時間ほど正座させられ叱責されたことでした。
当クリニックでも、子どもたちが「頭痛」「腹痛」などの症状を訴えるケースがあります。胃腸炎や感冒などが否定された場合、学校の悩みもありますが、ご両親が教育熱心なあまり、子どもたちに必要以上の勉強を期待する場合があります。その時はご両親に勉強時間を減らすようにお伝えたりします。結果子どもたちの訴えが改善することがあります。事件にまでならない場合でも、「教育虐待」に近いことは身近にあります。親がよかれと思っていても、子どもは深く傷つき、自信が低下し、うつや不安などの精神症状、体調不良を認める場合があります。勉強だけでなく、スポーツや音楽もあてはまります。
教育虐待の背景と防止策
2024年3月13日、NHKクローズアップ現代「教育虐待、その教育は誰のため?」の番組の中で一般社団法人ジェイス代表理事武田信子さんの話がありました。「教育熱心」でありたいと思いながらも「教育虐待」につながることがある。「教育熱心」である場合は、親は子どもをそもそも別の人格だと考え、子どもが幸せな状態かを第一に考えて、無理ならば別の道を考えます。「教育虐待」は自分の子どもは自分の作品と思い、子どもと自分の成功が大切でその道を良かれと信じて疑わないようになる。教育虐待の背景には「親の不全感(親の理想を実現できていない)」・「子どもの人生は親の責任」・「競争的な社会」があります。そのため、親の子どもへの向き合い方として「子どもを尊重する」・「対話できる関係作り」が大切だと述べています。子どもの気持ちに寄り添い、親の言う通りにするのではなく「それで、どう思っているの?」というやり取りをする。このような対話をずっと繰り返すことで、親が決定しないで子どもを尊重できる。このやり取りを繰り返していくと信頼関係が作られると言っています。
私の経験から
私自身も子どもに教育虐待に近い?ことをしたことがあります。子どもが中学生の時、暴力はしませんでしたが、言葉で強く「勉強しろ!」と言ったことが何度か(もしかしてもっとかも?)あります。そうすると家庭が冷え切りました。親として子どもに過度の期待をしてしまったことが自分自身の反省点です。その経験から学んだのは「子どもは自分とは別人である」「子どもは学校などで勉強するように言われている」ことです。親ができることは、見守って応援してあげることだけでよいことを知りました。中1の娘にはそれだけを心がけています。親は子どもに尽くすことだけが責務ではありません。子どもが成人になってもよい親子関係を保つことで、お互い助け合う関係もできます。やがて子どもは老いていく親をサポートしてくれるでしょう。親業を楽しみましょう。