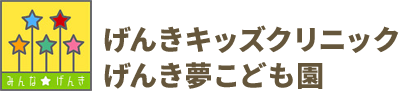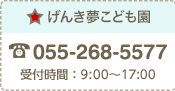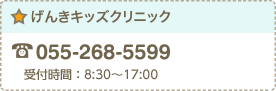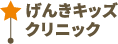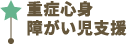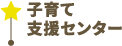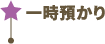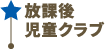令和7年10月号(Vol.245)<br>消化管アレルギー(食物蛋白誘発胃腸炎)について
今年の夏は本当に暑かったですね。35℃以上の最高気温が連日続き、体にとても応えました。
さて、2学期に入って園・学校生活に慣れないお子さんが、腹痛、頭痛を訴えうちのクリニックに受診します。運動会の練習で疲れている子どもたちもいます。園・学校でがんばった分、家でゆっくりと体を休ませてあげてください。家で充電できれば、翌朝は元気になって飛び出していけます。また必要に応じて子どもたちの訴えを聞き、園・学校に協力していただき調整をしている子どももいます。小児科医として子どもの代弁者であり続けたいと思っています。
さて、私のマイブームをお伝えします。10年前、自宅の屋根に太陽光パネルと設置し、その電気を活かして自宅の電気を一部賄っています。さらに数年前、ネット通販店で太陽光パネルと蓄電池を購入。その蓄電池を利用して、自宅の扇風機、スマホの充電、洗濯機、電子レンジなどで使用し、なるべく既存の電気を利用しないように工夫しています。小さなことですが、少しずつ気にすれば、電気を作る原料となっている石油・石炭・原子力などの軽減化に寄与できるのではないかと自己満足に浸っています。
今月は、ここ20年くらいで世界的に増加している消化管アレルギーについて皆様にお伝えいたします。
消化管アレルギーって?
「消化管アレルギー」という言葉を耳にしたことがない方もいるかもしれません。消化管アレルギーは食物アレルギーの中で、嘔吐・下痢などの消化管症状を認める病気と言われています。以前までは病名がいくつも混在していました。患者数の増加で認知されるようになり、病名もようやく統一されるようになってきたのが現状です。
消化管アレルギーは新生児・乳児食物蛋白誘発胃腸症と好酸球性消化管疾患の2つに大きく分けられます。今回は、新生児・乳児食物蛋白誘発胃腸症のうち患者数が一番多い、代表的な病名である「食物蛋白誘発胃腸炎(≒消化管アレルギー)」について述べさせていただきます。
消化管アレルギーは新生児や乳児で原因となる食物(卵など)を摂取してからしばらくして、嘔吐や血便、下痢などの症状がみられます。皆様がよくご存じの(即時型)食物アレルギーはじんましんや咳・ゼイゼイなどがみられますが、消化管アレルギーは嘔吐・下痢などの消化器症状のみでじんましんなどの症状がないのが特徴的です。
原因食物・発症時期は?
2024年国立成育医療研究センターの研究結果で、消化管アレルギーの原因食物は鶏卵(58%)が最も多く、大豆(11%)、小麦(11%)、魚(6%)、牛乳(6%)、貝(4%)でした。鶏卵のうち94%が卵黄ということがわかりました。当院においても、原因食物では鶏卵の中で「卵黄」が非常に多い印象があります。また発症月齢は、牛乳が生後1ヶ月と最も早く発症し、続いて大豆6ヶ月・鶏卵7ヶ月・小麦8ヶ月でした。発症が遅くみられるものとして、魚36ヶ月・貝48ヶ月があります。別のデーターでは、初回摂取で症状がでる場合は頻度として少なく、複数回から発症する場合が多いと報告されています。私の経験でも初回発症でなく、3~4回目摂取して発症する場合が多いです。
診断、治療は?
国際的な診断基準があり、「主要基準」を満たした上で、「副基準」のうち3つ以上を満たした場合に診断されます。「主要基準」とは原因食物を摂取後1〜4時間後に嘔吐があり、(即時型)食物アレルギーで認められるような皮膚・呼吸器症状がないことです。「副基準」とは➀同じ食物を摂取した際に、繰り返す嘔吐が2回以上ある ②2つ以上の異なる食物に対して、摂取後1〜4時間後に繰り返す嘔吐がある ③極度の活力の低下 ➃血の気が引き青ざめる(蒼白) ⑤緊急受診の必要がある ⑥輸液をする必要がある ⑦食物摂取後24時間以内の下痢(通常5〜10時間後) ⑧血圧低下 ⑨低体温のうち3つ以上満たした場合に該当します。よくある例は、卵黄を食べ始めて数回試した時に、3時間前後に嘔吐を認め、そのエピソードを2~3回繰り返すことが診断のめやすになると考えられています。疑うことがこの病気の発見につながります。
治療は原因食物を除去をすることで、嘔吐などの症状はなくなります。その後、原因食物を解除する段階を考える必要があります。幸い、消化管アレルギーは予後良好と言われており、1~2歳で食べられる場合が多く、食物負荷テスト(医師の指示のもと少量から食べる)を病院で行い、症状がなければ除去解除でき完治できます。
参考文献
日本小児アレルギー学会. 食物アレルギー診療ガイドライン2012 協和企画
食物たんぱく誘発胃腸症(消化管アレルギー) 国立成育医療研究センターHP
https://www.ncchd.go.jp/hospital/sickness/children/allergy/gastrointestinal_allergy.html
Hayashi D, Yoshida K, Akashi M, et al. Differences in Characteristics Between Patients Who Met or Partly Met the Diagnostic Criteria for Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES). J Allergy Clin Immunol. 2024 Jul;12(7):1831-1839